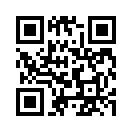2019/03/12
破壊的イノベーションが起きやすい国
 日本からのお客様とベトナムのGrabなどのシェアビジネスが現実のビジネスにどんな影響を与えているかという話でディスカッション。
日本からのお客様とベトナムのGrabなどのシェアビジネスが現実のビジネスにどんな影響を与えているかという話でディスカッション。日本は安全性の問題や規制がまず先に出てきてしまうので、なかなかこういうシェアビジネスは普及していきにくいでしょうねという話をしたら、
それはある意味、「イノベーションのジレンマ」かもしれないね
とのことだったので、不勉強で知らなかった僕はネットでイノベーションのジレンマについて検索してみました。
Wikipediaなどで読んでみると、イノベーションのジレンマというのはクレイトン・クリステンセンという方が提唱した理論のようで、いわゆる大企業病と言われるようなものみたいです。
イノベーションには、既存の改良である「持続的イノベーション」と、既存の価値を破壊して全く新しい価値を生み出す「破壊的イノベーション」というものがある中で、成熟した会社や国ほどこの「破壊的イノベーション」が起きにくくなってしまうそうです。
21世紀の例でいうとIphoneしかり、破壊的イノベーションが起こると一気に世の中の産業や生活が一変してしまうみたいなことが起きるし、その破壊者となった企業には莫大な富を生むことになるし、その破壊的イノベーションに乗り遅れると、デジカメの普及で潰れたコダックのように一気に企業が消えてしまうようなことすらおきうるとのこと。
破壊的イノベーションの前に参入が遅れる5つの原則としては下記のものがあるそうです。
・企業は顧客と投資家に資源を依存している。
既存顧客や短期的利益を求める株主の意向が優先される。
・小規模な市場では大企業の成長ニーズを解決できない。
イノベーションの初期では、市場規模が小さく、大企業にとっては参入の価値がないように見える。
・存在しない市場は分析できない。
イノベーションの初期では、不確実性も高く、現存する市場と比較すると、参入の価値がないように見える。
・組織の能力は無能力の決定的要因になる。
既存事業を営むための能力が高まることで、異なる事業が行えなくなる。
・技術の供給は市場の需要と等しいとは限らない。
既存技術を高めることと、それに需要があることは関係がない。
日本のように成熟している国では良い意味でも悪い意味でもルールが網の目のように整備されていて、そこにみんながきちんと従うことで、社会が成立している中で、国にとっては顧客は国民や既存企業であり、彼らに一時的としても不便や不満を与えてまでも、ルールを変えて新しいことに取り組むというのは確かに難しいでしょうが、
逆にベトナムのような発展途上国はそもそも今のルールやサービスでは不便や不満だらけみたいなことがいっぱいあり、破壊的イノベーションを受け入れやすい土壌なのだろうなと。
以前にも紹介したバイクドライバーのおっちゃんたちの姿はまさにこの破壊的イノベーションに乗り遅れた象徴なので。
2018/06/16
今のGrabなどのライドシェアに限らず、ベトナムは今後も破壊的イノベーションが様々な分野で発生して、一気に産業構造が変わるなんてことがあり得るのでしょうね。
ベトナムの次の破壊的イノベーションはどの分野で起こるのかちょっと楽しみです。
Posted by いのっち at 15:33│Comments(0)